スケーラビリティとは
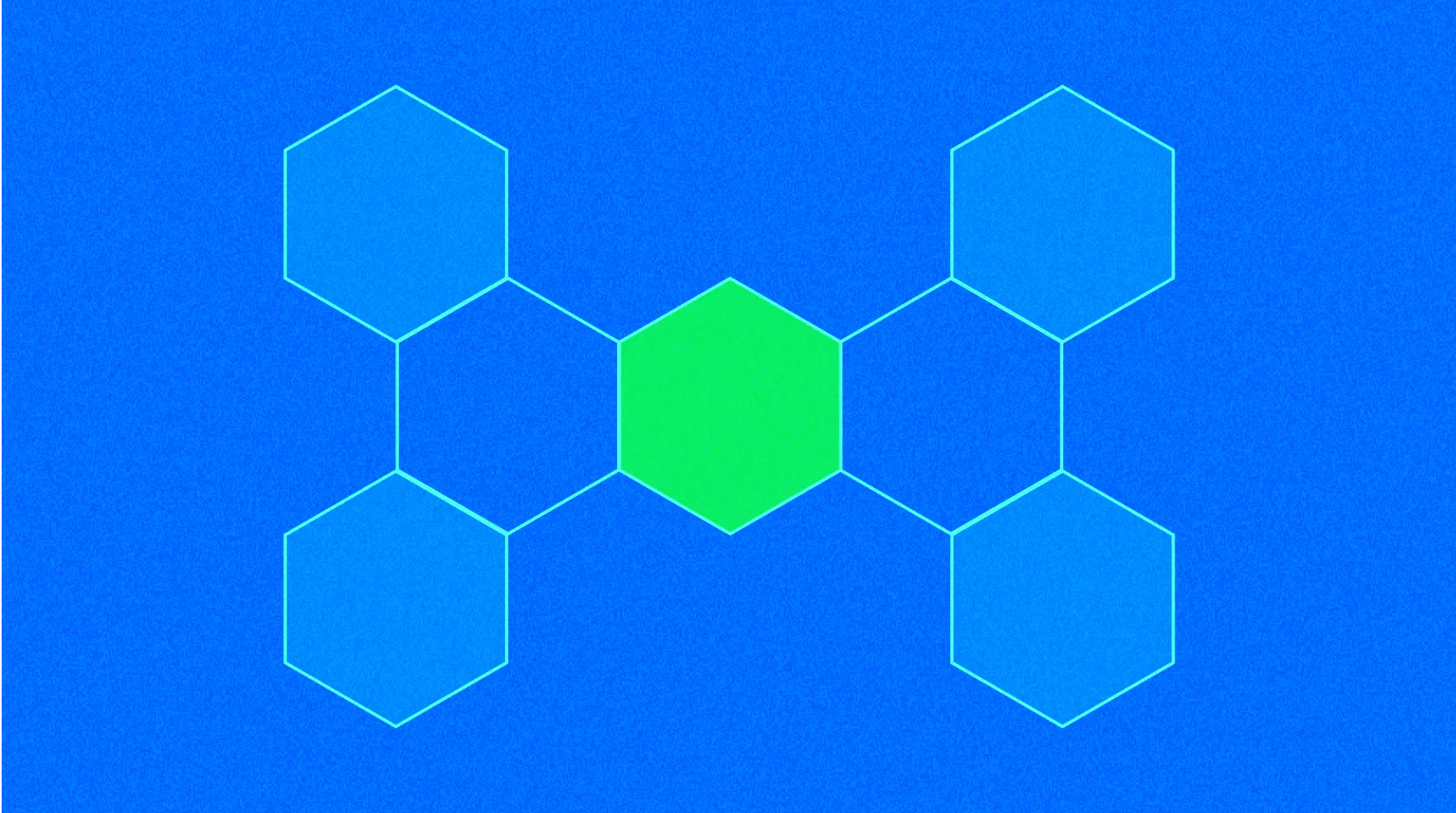
スケーラビリティとは、ブロックチェーンネットワークがトランザクションの増加やユーザー数の拡大に対して、パフォーマンスとセキュリティを維持しつつ対応できる能力を指します。これはブロックチェーン技術が直面する主要な課題の一つであり、暗号資産や分散型アプリケーション普及の鍵を握る重要な要素です。高いトランザクション処理能力を維持しながら、分散性とセキュリティを損なわないことは、いわゆる「ブロックチェーントリレンマ」(分散性・セキュリティ・スケーラビリティの三要素を同時に達成することが困難であるという課題)に深く関わっています。
スケーラビリティ問題の背景には、ビットコインネットワークの初期設計に起因する制約があります。ビットコインではブロックサイズが1MBに設定され、約10分ごとに新たなブロックが生成されるため、理論上の最大処理能力は毎秒約7トランザクションに限られています。ユーザー数が増加すると、この制約が顕在化し、グローバルな決済システムとしての需要に応えるためのスケーリング手法を巡って活発な議論が巻き起こりました。特に2017年のブロックサイズ論争は、ビットコインがビットコインとビットコインキャッシュに分岐するきっかけとなったことで有名です。
技術的な観点から見ると、ブロックチェーンのスケーラビリティ向上策は主にレイヤー1(オンチェーン)スケーリングとレイヤー2(オフチェーン)スケーリングに分類されます。レイヤー1の手法では、ブロックチェーンプロトコル自体を改良し、例えばブロックサイズ拡大やブロック生成間隔の短縮、効率的なコンセンサスメカニズムの導入が行われます。Ethereumがプルーフ・オブ・ワークからプルーフ・オブ・ステークへ移行したのは、スケーラビリティ改善を大きな目的としたものです。レイヤー2では、ビットコインのLightning NetworkやEthereumで用いられるロールアップのように、メインチェーン外部に追加レイヤーを設置することで、膨大なトランザクションをオフチェーンで処理し、最終的な結果のみをメインチェーンに記録します。これにより、メインチェーンの負荷を大幅に軽減できます。
スケーラビリティに関する主な課題には、技術的な複雑性、分散性と効率性のバランス、さらには相互運用性の問題が挙げられます。トランザクション処理能力の向上には高性能なハードウェアや複雑な検証方式が必要となり、結果的にネットワーク参加者の障壁が高まり、分散性の低下につながることもあります。また、多様なスケーリングソリューション同士の互換性の問題もエコシステム全体の発展を阻害しています。シャーディングやクロスチェーンソリューション、新たなコンセンサスアルゴリズムの開発が進むことで、ブロックチェーンのスケーラビリティは徐々に向上していますが、業界の大規模展開を阻む要因として依然として重要です。
株式
関連記事


ブロックチェーンについて知っておくべきことすべて
